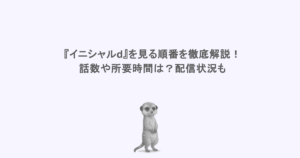愛する子どもたちを守るため、DV夫を殺害した母親が15年ぶりに帰ってくる。しかし、その「一夜」の出来事は決して「父親の暴力からの解放」だけを意味するものではなかった。人殺しの子どもというレッテルを貼られて生きてきた3人は、帰還した母親とどう向き合うのか。
白石和彌監督らしい、息の詰まるような緊張感の中で変質してしまった家族模様が描かれる。佐藤健、鈴木亮平、松岡茉優、田中裕子。たった一夜の出来事で人生が大きく狂ってしまった彼らの物語は、ヤクザから足を洗った男の悲劇と見事なコントラストを描き、呪いにも似た「家族」という関係性に、一先ずの終止符を打つ。
原作は劇作家の桑原裕子の脚本。そのせいもあってか、無線のシーンのような舞台的な演出が目立つ。私は観劇していないが、この重苦しさが直で肌に伝わってくるとしたら、それは相当な打撃だろう。母の行動は彼女にとっては救済であり、映画の表現を借りるならば彼女は聖母になったはずだった。しかしどんな理由があろうと、それは結局殺人でしかない。何の相談もなく突然人殺しの子どもになってしまった3人は、いつも心のどこかで「母親があんなことをしなければ」と思って生きてきた。そんな母と子の断絶と、子3人の価値観の違い、それぞれが持つ表と裏の顔が心を激しく揺さぶる。とにかく凄まじい映画だ。
小説家になるはずの次男・雄二は週刊誌の三流ライターに、吃音を持った優しい長男・大樹は妻と離婚寸前、美容師になる夢を持っていた園子は地元のスナックで働いていた。親のタクシー会社は叔父が引き継いでおり、そこに堂下(佐々木蔵之介)が新しく入社する。そんなある日、3人の母こはるが帰ってくる。「戻らない方がいいんじゃないかと思った時もあった」と語る母に、大樹と園子はどう接していいか分からず戸惑う。とりあえず東京に出た雄二に電話をかけ、帰ってくるように頼んだ。
こはるの帰宅を歓迎するタクシー会社の人々。園子と大樹もこはるの決意を汲み取って気さくに接するが、雄二はそうはいかない。食事のシーンだけでも、3人のぎこちなさから伝わる重苦しい空気感。雄二はインタビュアーさながら、こはるに「何しに帰ってきたんですか」と問いかける。彼が東京に出たのは、事件のせいで町に住みづらくなってしまったからだった。
一方、働いている大樹の元には毎日のように妻がやってきて離婚を申し出る。断固として離婚に応じない大樹だったが、妻がこはるの事件を知って「娘が人殺しの孫なんて!」と言われると態度が豹変。怒りのままに離婚届を記入し、なおも激昂する妻の顔を思いっきり叩く。誰よりも優しく、喧嘩の仲裁係だったはずの大樹が、実は最も父親に近かったという皮肉。一部始終を目撃していたこはるからも、「父親と同じ」だと指摘されてしまう。
そして、その言葉が更に大樹を刺激する。「母さんは、立派だから!」と声を荒げる大樹。父親を殺してまで子どもたちを守ろうとした母の行動は、大樹にとっては眩しすぎたのである。吃音で言葉が不自由な上に、妻や子どもともうまくいかない。そんな苦悩の矛先は、いつしか母親に向いてしまっていた。それを聞いた母親は、「自分は立派なんかじゃない」とかつて雄二がやったようにコンビニでエロ本を万引きする。その行動にフォローを入れる丸井の役割も重要だ。
一方、新しく入社した堂下は、一見真面目な男に見えるが実は子どもとの間に蟠りを抱えていた。久々に再会した高校生の息子と語り合い、焼肉を食べ、バッティングセンターでふざけ合う。この幸福な時間こそ、彼にとっての「ひとよ」だったのである。最後には会社から前借りした10万を渡し、笑顔で息子を見送る。しかし数日後、彼の元に怪しげな男が現れる。実は堂下は元ヤクザで、男は堂下の元部下だった。意図せずクスリを運ぶことになった堂下は、「今回だけは見逃してやる」と言い残す。後日、指定の場所に赴くと、若い運び屋がタクシーに乗ってくる。その顔を見て愕然とする堂下。なんと運び屋は愛する息子だったのだ。
「蛙の子は蛙」。自分が息子を幸せにしてやろうと積み重ねてきた努力は、全く無意味だった。絶望した堂下は、刺青のある腕を隠そうともせず、飲酒運転をする。その助手席には、自分の行動により子どもたちがどれだけ苦しんだか理解してしまったこはるが乗っていた。自暴自棄になった2人は、そのまま海に身を投げようとしたのである。
こはるが危ないと、急いで堂下を追う雄二たち。奇しくもそれは、こはるが警察に出頭したあの夜と同じシチュエーションだった。しかし、今度は逃がしはしない。確実に母親を止める。決死のカーチェイスの末、真横から追突することでなんとか自殺を食い止めることに成功した。
そこで激しく揉み合う堂下と雄二。「親がどれだけ子を想って行動しても、子どもには伝わらない」と嘆く堂下。しかし、だからこそ何気ない時間を過ごしたあの夜のことが忘れられない。「あの夜は一体なんだったんだ!」という慟哭が観客の心に突き刺さる。対する雄二は、母親への感情をぶち撒ける。「自由に生きていいんだよ」といえ母の言葉と行動は、彼にとっては枷になっていた。「母さんが人殺してまで作ってくれた自由なんだよ!」。雄二は事件の後、母親のネタをダシに出版社へ潜り込み、日銭を稼いでいた。その記事が会社への嫌がらせに使われていたのである。園子たちは、全ての元凶は雄二であると責めるが、それには彼なりの理由があった。
母親が与えてくれた自由を謳歌するため、夢だった小説家になるため、彼はたとえ邪なやり方だとしてもその道を選んだのである。だからこそ、夢を諦めた園子や前に進もうとしない大樹とうまくいかなかった。こはるが救済のつもりで犯した殺人は、雄二を蝕み苦しめてしまったのだ。最後、東京に戻る雄二を見送る家族。心の中のモヤモヤを全てぶち撒けた彼らは、新たに家族として再生したのであった。
重い。何度でも言うが非常に重い物語である。子どもを救うために暴力夫を殺害した母親というだけで十分重いのに、その事件の見え方に齟齬が生まれることでより重厚になっている。家族のギスギスを描いた物語は結局、誤解を解いたり単純な仲直りで元に戻ってしまう作品が多いが、この映画はそうではない。誤解も一切なく、すれ違いはそのままに新たな家族として再生する姿を描く。一つの事件の見え方がキャラクターによって異なるというサスペンス的な魅力も持ち合わせている。
「母さんのせいだ」と「母さんのために」が渦を巻き、あの事件のない世界に想いを馳せる姿が哀しく映る。「暴力に耐えればよかっただけ」という言葉もまた真理かもしれない。だが、起きてしまったことは変えられない。彼らは事件を受け入れて生きるしかないのである。たった一夜で人生が狂ってしまった彼らが、それぞれ本音をぶち撒ける姿は涙を禁じ得ない。何度も吐きそうになりながら、人間の脆さと美しさにガツンと脳天を叩かれる。観た後には必ず家族との向き合い方を見直したくなる映画だ。